漏電とはどんな現象なの?仕組みや原因、安全に防ぐ基本ポイント

―「ブレーカーが頻繁に落ちる」「電気代が急に上がった」
それ、漏電のサインかもしれません。
漏電は感電や火災の原因となる危険な現象で、放置すれば命や財産を脅かします。
本記事では、漏電の仕組み・原因・確認方法を初心者向けに徹底解説。
さらにショートとの違いや、漏電が起こったときの対処法まで網羅しているので、電気設備の安全管理に必要な知識がこれ一本で身につきます。
こんな方におすすめ:
- 電気設備の保全・管理業務に携わる方
- 漏電の兆候を見逃さず早期対策したい方
- 工場や施設で漏電監視装置の導入を検討中の方
漏電とは?仕組みと意味をやさしく解説
漏電とは、電線や電気機器の損傷した絶縁部から、本来流れるべきではない経路に電流が流れ出る現象です。感電事故や火災につながる危険な状態で、原因は絶縁体の劣化、水濡れ、ホコリの蓄積などが挙げられます。
漏電を正しく理解し、早期発見・対策を行うことは、電気設備の安全維持にとって非常に重要です。ここでは、漏電の基本的な意味や発生の仕組み、ショートとの違いについて、わかりやすく解説します。
関連記事
▷絶縁監視装置の導入で防ぐ火災・家電事故|基礎から選定基準まで

漏電とは何か?基本の定義
漏電とは、電気が本来流れるべき導線や回路ではなく、絶縁されていない箇所を通じて外部に電流が流れ出る状態を指します。経済産業省や電気保安協会なども「漏電」を「絶縁不良により本来の電路以外の部分に電流が流れること」と定義しています。つまり、電気機器や配線の経年劣化、損傷、水濡れなどによって絶縁が不完全になり、電気が漏れる状態です。
理由としては、絶縁材料の劣化や破損、湿気や水分の侵入、小動物によるかじりなど、外的要因が重なることで絶縁不良が発生します。特に古い建物では、配線の劣化が進んでいるケースが多く、注意が必要です。
例えば、コードの外皮が破れて金属部分が露出した状態で床に水があると、そこを電気が流れてしまい、周囲の人が感電する可能性があります。
結論として、漏電は私たちの身の回りに潜む非常に危険な現象であり、放置すれば感電事故や火災のリスクを招きかねません。日常生活で気づきにくい分、正しい知識が必要です。
漏電とはどんな仕組みで起こるのか
漏電の仕組みは、「絶縁不良」がキーワードです。電気は絶縁体によって回路外へ流れないよう保たれていますが、何らかの理由でこの絶縁が破れると、電気は漏れ出します。
漏電は大きく2種類に分けられます。「線間漏電」は配線同士の間で漏れるもので、「地絡漏電」は接地(地面)に向かって電気が流れるものです。とくに後者は人体を介して感電するリスクがあり、危険性が高くなります。
結論として、漏電は「絶縁が破れたときに、意図しない方向に電気が流れる」という単純かつ重大な仕組みで発生します。正しい対策のためにも、この仕組みの理解は欠かせません。
漏電とショートの違いとは
漏電とショート(短絡)は、混同されやすい電気トラブルですが、仕組みもリスクも異なります。
漏電は電気が「外部に漏れる」現象で、外装の破損や湿気などにより、外に電流が流れる状態です。
関連記事
▷漏れ電流とは?仕組み・測定方法・危険性・対策まで徹底解説
一方ショートは、本来繋がってはいけない電線同士が直接接触し、大量の電流が一気に流れる現象です。
たとえば、漏電は水滴がコードに付着して電流が床に逃げるようなケース、ショートはコンセント内部でL(電圧)とN(中性線)が直接触れてブレーカーが落ちるケースが該当します。
どちらもブレーカーが作動して遮断される場合が多いですが、ショートは一瞬で高電流が流れるため火花や発火のリスクが高く、漏電はじわじわとした危険が蓄積していくイメージです。
漏電とショートの比較表
| 項目 | 漏電 | ショート |
|---|---|---|
| 発生の仕方 | 絶縁劣化・湿気・外装破損によって、 電気が外部に漏れる |
電線同士が直接接触して回路がつながる |
| 電流の大きさ | 比較的小さいが持続的 | 非常に大きな電流が一気に流れる |
| 危険性 | 感電・火災リスクが徐々に高まる | 火花・発火など瞬間的に重大事故につながる |
| ブレーカーの反応 | 漏電遮断器(ELB)が作動し遮断 | 配線用遮断器(MCB)やヒューズが即座に作動 |
| 発生例 | 水滴がコードに付着して床に電流が逃げる | コンセント内部でLとNが直接接触し火花が出る |
結論として、漏電は”じわじわ進む見えない危険”、ショートは”一瞬で起こる衝撃的な危険”といえます。
両者の違いを正しく理解することで、トラブル発生時に迅速かつ適切な対応が可能になります。
漏電とは危険なのか?主なリスクと症状
漏電は非常に危険な現象であり、早期の発見と対処が求められます。一般家庭から工場まで、漏電が原因で起こるトラブルは感電事故や火災など命に関わることも少なくありません。このセクションでは、漏電が引き起こす具体的なリスクと、初期に見られる症状について解説します。
漏電とは感電や火災の原因になる現象
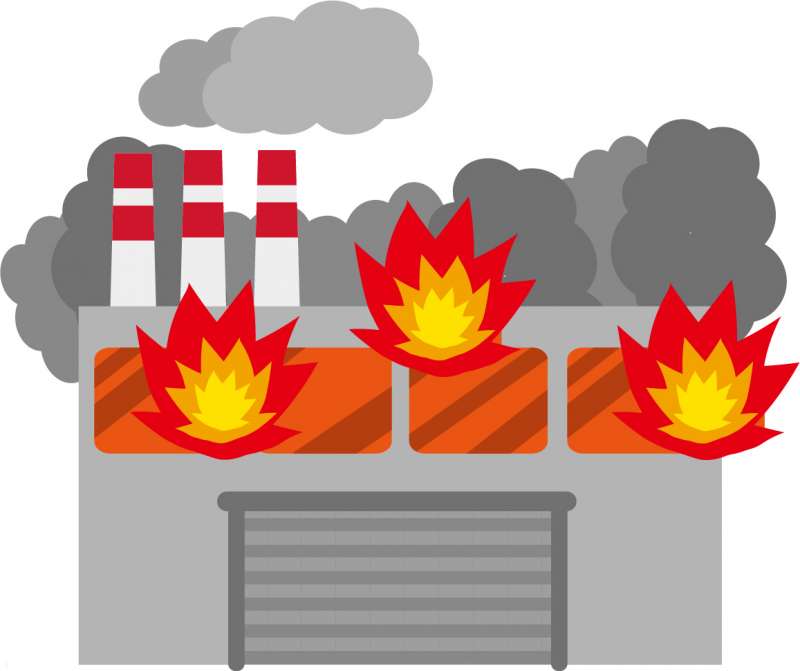
結論から言えば、漏電は感電・火災のどちらも引き起こす可能性のある危険な現象です。感電事故に関しては、厚生労働省の「職場における感電災害事例」によると、電気機器の漏電が原因で作業者が死亡した事例も報告されています。
漏電によって外部に流れた電流が人体に接触すると、筋肉のけいれんや心停止を引き起こす可能性があります。特に濡れた手で電化製品を触った場合や、屋外での作業中に漏電した機器に触れた場合などは、感電の危険が高まります。
感電によって人体へ電流が流れると、電流の大きさ、人体を通過する時間、通電経路によって、人体への影響は「ピリッと」感じる程度から、火傷、死亡といった重大な結果にまで及びます。
| 電流値 | 人体への影響 |
|---|---|
| 0.5mA~1mA | 最小感知電流、「ピリッと感じる」 |
| 5mA | 相当の痛みを感じる |
| 10~20mA | 離脱の限界、持続して筋肉の収縮が起こり、体を離すことができなくなる |
| 50mA | 気絶、人体構造損傷の可能性、呼吸器系等への影響、心肺停止の可能性も |
| 100mA | 心室細動の発生、心肺停止、極めて危険な状態に |
また、漏電により異常発熱が生じた場合、それが可燃物に接触すれば火災につながります。
東京消防庁の統計でも、電気火災の原因の約3割が「漏電」によるものとされています。
実際に、1955年10月に新潟市で発生した「新潟大火」は漏電が原因で、1000戸以上の家が焼けるという甚大な被害をもたらしました。
結論として、漏電は日常の中に潜む非常に危険な現象であり、放置していると命や財産を脅かす重大事故につながりかねません。
漏電が起こると出る症状の例
漏電は目に見えない現象ですが、日常生活の中でいくつもの兆候として現れます。こうしたサインを見逃さず、早めに対策することが安全確保に直結します。代表的な症状は以下の通りです。

漏電の主な兆候
・ブレーカーが頻繁に落ちる
特に漏電遮断器(ELB)が作動している場合、漏電による異常電流を検知して電源を遮断しているサインです。
・特定の家電を使用すると停電が起こる
家電内部の配線や絶縁不良が原因で漏電している可能性があります。
・電気代が急に上昇する
実際は使ってはいないのに電流が流れ続けるため、消費電力が増加しています。
・家電製品やコンセントに触れるとピリピリとした違和感がある
微弱な電流が外部に漏れており、人体に伝わっている状態です。
・建物の金属部分に触れるとビリビリ痺れる感覚がある
アース不良や配線の劣化で金属部分が帯電している場合に起こります。典型的かつ危険な漏電の兆候です。
・湿気の多い場所で電気トラブルが頻発する
浴室、キッチン、洗面所などでは絶縁性能が落ち、漏電が起きやすくなります。
より注意すべき危険なサイン
・電球がチカチカする、照明が安定しない
電圧が不安定になり、照明に影響が出ている可能性があります。
・スイッチを入れた瞬間に火花(スパーク)が出る
配線やスイッチ内部の劣化により漏電が進んでいる危険信号です。
・コンセント周辺から焦げ臭いにおいがする
漏電に伴う発熱が原因で、火災につながる非常に危険な状態です。
・コンセントや電源タップが異常に熱くなる
漏電や過電流によって発熱している可能性があります。
・雨の日や湿気の多い日に限ってブレーカーが落ちる
屋外配線や外部設備に水分が入り込み、漏電しているケースです。
これらは、いずれも「何かしらの電気が意図しない経路で流れている」可能性を示しています。特に、頻繁にブレーカーが落ちる現象は「漏電遮断器(ELB)」が作動しているサインであり、電気工事士に点検を依頼すべき重要な警告です。
また、電気代の急増も漏電の見落としがちな症状の一つです。漏電により常に電気が流れている状態となり、使用していないにも関わらず消費電力が増加しているケースがあります。
もし漏電のサインを見つけたら?緊急時の対応フロー
漏電は火災や感電につながる恐れがあるため、放置は非常に危険です。症状を発見したら、以下の手順で落ち着いて対応しましょう。
1.安全確保のため、すぐにブレーカーを切る
感電や火災を防ぐために、まずは建物全体の主幹ブレーカーをオフにします。
このとき、手が濡れている場合は必ず拭いてから乾いた状態で操作してください。
2.漏電が疑われる家電やコンセントには触れない
火花や異臭がしている部分は特に危険です。素手で触らず、そのままの状態を保ちます。
3.専門業者(電気工事士)に連絡する
自己判断で配線や機器を修理するのは危険です。必ず資格を持つ専門業者に点検・修理を依頼しましょう。
4.火災や煙が出ている場合はすぐに119番通報
漏電が原因で火災が発生している可能性があるため、ためらわず消防に通報してください。
漏電の症状は軽微な違和感から深刻な危険信号まで幅広く現れます。
「いつもと違う」と感じた時点で放置せず、まずは安全確保、その後に専門業者への相談を行うことが何より重要です。
漏電を放置するとどうなるのか
漏電を放置したままにすると、次第に症状は悪化し、最終的には重大な事故につながります。
漏電が進行すると、電線の温度が上がり続け、やがて発火に至る可能性があります。また、接地していない機器が漏電を起こすと、電気が筐体や金属部分に蓄積され、触れた瞬間に感電するリスクも増します。これは「地絡事故」と呼ばれ、工場や大型施設では特に警戒すべき現象です。
さらに、工場などの大型設備では、漏電による設備のダウンや、ライン停止などの経済的損失が発生する可能性もあります。前述のように、Ior(危険な成分)だけを正確に検出する「Leakele」のような絶縁監視装置を導入することで、放置による深刻な影響を未然に防ぐことができます。
結論として、漏電を軽視することは非常に危険です。小さな異常が大きな事故につながる前に、予防と点検を徹底することが重要です。次章では、漏電の原因についてさらに深く掘り下げて解説します。
漏電とは何が原因で起こるのか
漏電の原因は一つではなく、日常生活や工場の運用環境におけるさまざまな要因が関係しています。ここでは、代表的な3つの原因について具体的に解説し、対策の重要性を理解できるようにします。
コードや機器の劣化が漏電の原因に
漏電の最も一般的な原因の一つが「配線や電気機器の経年劣化」です。ビニールやゴムで絶縁されたコードも、長期間の使用や物理的なダメージにより表面が破れたり、内部が露出することがあります。
古い工場では、配線そのものが規格外だったり、当時の施工が今の基準に合っていないケースも多く、特に注意が必要です。また、電気機器も年数が経つと内部の基板やコンデンサなどが傷み、絶縁性能が落ちて漏電することがあります。
例えば、10年以上使用している設備の漏電ブレーカーが落ちるような場合、漏電が疑われます。長期間使われている機器には定期点検が不可欠です。
結論として、電線や家電の寿命は漏電リスクに直結するため、古い設備は早めの点検・更新が重要です。
水濡れ・湿気・雨漏りが引き起こす漏電

湿気や水分も漏電の大きな原因です。電気は水を通じて容易に流れるため、浴室やキッチンなどの湿度が高い場所では特に注意が必要です。
また、屋外に設置された電気機器や分電盤が雨にさらされることで、内部に水が侵入し、絶縁が破れて漏電が発生するケースもあります。屋根や壁からの雨漏りが配線に染み込むと、知らないうちに危険な状態になる可能性もあります。
特に工場や施設では、屋外のキュービクルに水が入り込んだ場合、大規模な電気トラブルへと発展しかねません。そのため、キャビネットの防水処理や、設置場所の見直しも漏電対策の一環です。
結論として、水濡れや湿気は「気づかぬうちに起こる漏電」を引き起こす要因であり、早期の防水対策と定期的なチェックが不可欠です。
ネズミなど小動物による漏電の事例
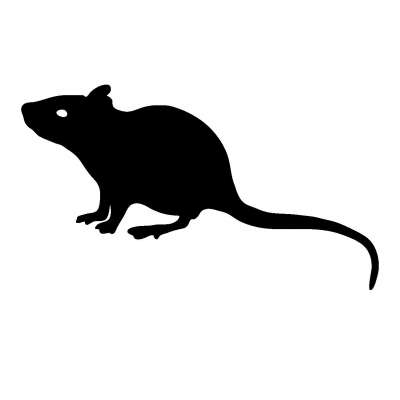
小動物、特にネズミによる被害も漏電の意外な原因です。ネズミは電線の被膜をかじる習性があり、絶縁体が破れて中の銅線がむき出しになると、そこから電気が漏れ出します。
実際に、工場や倉庫でネズミによる配線トラブルが頻発しており、特に屋根裏や床下などの人目につかない場所では被害に気づきにくくなります。小動物の尿によって腐食が進むケースもあり、見えないところで危険が進行していることもあります。
このような問題を防ぐには、防鼠処理や電線の保護チューブ設置が効果的です。また、ネズミの侵入経路を塞ぐ建物管理も重要です。
結論として、漏電の原因は人為的なものだけでなく、自然・動物的要因にも及ぶため、包括的なリスク管理が求められます。
漏電とは自分で確認できるのか?方法と手順
漏電が疑われる場合、自分で確認する方法はいくつか存在します。ただし、安全が最優先であるため、自己判断に頼らず必要に応じて専門業者への依頼が必要です。
ブレーカーを用いて調べる
もっとも手軽な方法が「漏電ブレーカー(漏電遮断器)」の確認です。分電盤内のブレーカーが頻繁に落ちる場合は、漏電の疑いがあります。
手順としては、すべての子ブレーカーを切った状態で主幹ブレーカーを上げ、一つずつ子ブレーカーを上げながら、どこで遮断が起きるかを確認します。異常が出る回路を特定できれば、どの機器または配線に問題があるかを推測できます。
ただしこの方法はあくまで簡易的な確認であり、安全に十分配慮した上で実施する必要があります。
結論として、ブレーカーによる調査は「第一歩」として有効ですが、最終判断にはプロの点検が欠かせません。
監視装置・テスターで計測する
より詳しく確認したい場合は、漏電測定テスターや「絶縁抵抗計(メガー)」を使用する方法があります。
また、最近では危険成分(Ior)のみを正確に検出できる装置もあり、これを活用することで誤検知を防ぎながら正確な漏電状況を把握できます。
漏電が疑われるときの業者への相談タイミング

少しでも異常を感じたら、早めに専門業者へ相談するのが最善です。感電や火災を未然に防ぐには、素人判断を避けることが大切です。
例えば、異常な電気代、触れるとピリピリする感触、湿気の多い場所での停電、機器の異常作動などが頻発する場合は、漏電の兆候と見なされます。これらが複数重なる場合は特に要注意です。
また、工場や施設で漏電監視システムを導入していない場合は、早急に検討すべきです。さらに、IoT機器と連携させることで、リアルタイム監視やアラート通知も可能になり、トラブルの未然防止に直結します。
結論として、早期の専門業者への相談は、被害を最小限に抑える重要な手段であり、「気づいた段階」でのアクションが求められます。

